池上町(いけがみちょう)
池上町のだんじり紹介


| 宮入神社(みやいりじんじゃ) | 曽禰神社(そねじんじゃ) |
| 新調年(しんちょうねん) | 平成6年 |
| 大工棟梁(だいくとうりょう) | 大下 孝治(おおしたたかはる) |
| 彫師(ほりし) | 木下彫刻工芸(きのしたちょうこくこうげい) |
| 土呂幕(どろまく)正面 |
賤ケ嶽秀吉本陣佐久間の乱入 (しずがたけひでよしほんじんさくまのらんにゅう) |
| 土呂幕(どろまく)右側 |
九州征伐加藤清正新納武蔵守決戦 (きゅうしゅうせいばつかとうきよまさにいろむさしのかみけっせん) |
| 土呂幕(どろまく)左側 |
単騎部下を救出する木村長門守重成 (たんきぶかをきゅうしゅつするきむらながとのかみしげなり) |
| 見送(みおく)り |
難波戦記(なんばせんき) |
特徴
池上町には、かつて池上神社・上泉神社の2社がありましたが、明治43年にそれぞれ曽禰神社へ合祀されました。
その後、市制が始まり、曽禰神社は泉大津市、池上町は和泉市と定められたため、現在でも池上町は市を越えて宮入し、また泉大津の連合へ参加しています。
地車の特長は池上曽根遺跡にちなんで、勾欄合に「弥生時代の生活風景」、また番号持には「やよいの大井戸に腰を掛ける卑弥呼」が彫刻されています。
- このページに関するアンケート
-
より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。

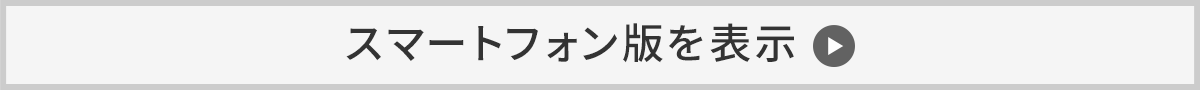
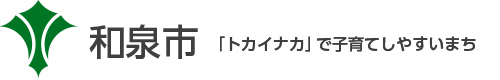


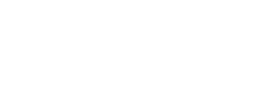
更新日:2025年03月21日