小社之町(うぐすのちょう)
小社之町のだんじり紹介


| 宮入神社(みやいりじんじゃ) | 泉井上神社(いずみいのうえじんじゃ) |
| 新調年(しんちょうねん) | 令和6年 |
| 大工棟梁(だいくとうりょう) | 泉谷 浩文(いずたに ひろふみ) |
| 彫師(ほりし) | 前田 曉彦(まえだ あきひこ) |
| 土呂幕(どろまく)正面 | 平清盛弁財天に戒められる(たいらのきよもりべんざいてんにいましめられる) |
| 土呂幕(どろまく)右側 | 九州千代川合戦(きゅうしゅうちよかわかっせん) |
| 土呂幕(どろまく)左側 | 三井寺の戦い(みいでらのたたかい) |
| 見送(みおく)り | 衣川の合戦 義経白龍伝説(ころもがわのかっせん よしつねはくりゅうでんせつ) |
特徴
先代地車が100年を迎え、令和6年10月に新たな地車を新調しました。
正面に源平の女性武将を揃えるなど、随所にこだわった見ごたえのある彫物と、美しい姿見は、我が町自慢の地車です。
小社の地名について
小社天神社の所在と関わってのものと考えられ、延宝7年(1677年)の府中検地帖では「をこそ」と記されております。
「小=を」「社=こそ」
また「元禄13年(1700年)の家州史には「府中宇久須神社」とありますが、小社天神社とこの府中字久須神社とは同じものかどうか不明であるものの、このオコソからオグスそしてウグスと変化したものと推測されます。 (小社之町地車百周年記念誌より引用)
彫物について
- 正面五層彫土呂幕
弁財天の御光を再現する為に、天井に金箔を貼る細工を施しています。
- 右松良、正面大連子、左松良
倶利伽羅峠の戦いで構成されていて、松良巴御前と松良山吹御前が大連子葵御前を狙うさまは、他に類を見ない彫物構成になっています。
- 番号持について
我が小社之町は府中西町会であります。
故に、番号持ちは和泉の清水と西の方角にちなみ水と西の方角の神 水天です。
幟台も四神獣の西の守り神白虎です。
- 見送り
義経の化身白龍は白龍の白を表現する為、だんじり彫刻では珍しいケヤキでは無くヒノキで色を表現しています。
以上、これから100年、次の世代へ伝統を継承していきたいと思います。
この記事に関するお問い合わせ先
〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 市長公室 広報・協働推進室
電話:公民協働推進担当 0725-99-8103(直通)
ファックス:0725-41-1553
メールフォームでのお問い合わせ
- このページに関するアンケート
-
より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。

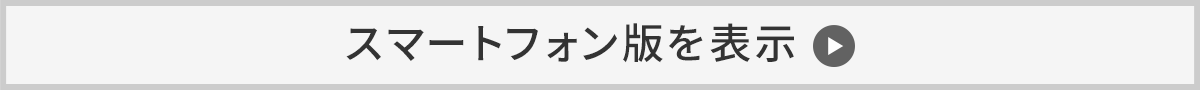
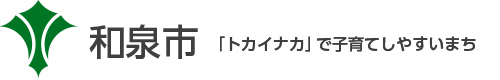


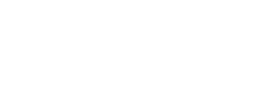
更新日:2025年03月21日