【いずみガラス】国の伝統的工芸品の指定を受けました!
和泉市の地場産品である「いずみガラス」が令和6年8月20日に開催された産業構造審議会商務流通情報分科会伝統的工芸品指定小委員会の審議を経て、令和6年10月17日付けで経済産業大臣より指定を受けました。
伝統的工芸品とは
下記5つの項目を全て満たし、伝統的工芸品産業の振興に関する法律に基づく経済産業大臣の指定を受けた工芸品です。
・主として日常生活の用に共されるもの
・その製造過程の主要部分が手工業的
・伝統的な技術又は技法により製造されるもの
・伝統的に使用されてきた原材料が主たる原材料として用いられ、製造されるもの
・一定の地域において少なくない数の者がその製造を行い、又はその製造に従事している者。
「いずみガラス」の概要
「いずみガラス」とは
・19世紀後半に技術が伝来し、20世紀初頭に技術が確立したガラス製品製造技術。
・軟質ガラスが素材のため、融点が低く、灯油ランプによるランプワークでの製造が特徴で、温度の調整幅が広いことから豊富なカラーバリエーションを実現できることが特徴。ガラスを巻き取って成形するため、職人の技術が問われる。
特徴
軟質ガラスを素材としているため、ガラスでありながら丸みを帯び、温かみが感じられる。
工程

・ガラス生地の製造
ガラスの主原料(珪砂・ソーダ灰(炭酸ナトリウム)・石粉・鉛)と着色剤(酸化金属(金、マンガン等))をアルミ製の「オケ」に入れ調合する。ガラスを溶解後、着色剤を投入する為、別々のオケで調合する。

・融解
「窯」に入れ1300℃で12~15時間かけて溶解する。時間をかけて溶解することで気泡がなくムラのないガラスとなる。溶解後、不純物が含まれる上澄み液を取り除き、着色剤を溶解する。

・棒引き
溶けている状態のうちに鉄の杭にガラスを引っ掛け、細長く引き伸ばし2本の棒状にする。

・カット
伸ばしたガラスの棒の表面が固まったら、一定の長さにカットする。

・ランプワーク
取り棒の先端にガラス生地を巻き取る。

・製造技法
1.取り棒に胴体となるガラスの塊を取る。
2.表情や前側の造形を製作する。
3.取り棒から外しピンセットで前側を掴む。
4.後足や後ろ側の造形を製作する。
完成品

【色ガラス棒】
ガラス生地は、その微細な組成の違いにより発色が異なる。
職人による金属の投入量、溶湯温度及び道具の熱伝導率の見極めにより、160色以上ものカラーバリエーションを実現している。




【アミ目細工】ランプワーク技術の集大成。
正確な工程どおりにパーツを組み上げ、網目の感覚の再現やパーチの組み上げ時のバランス等、細工の複雑であるため、分業での製作は難しく、一人の職人によって製作される。
関連資料
- このページに関するアンケート
-
より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。

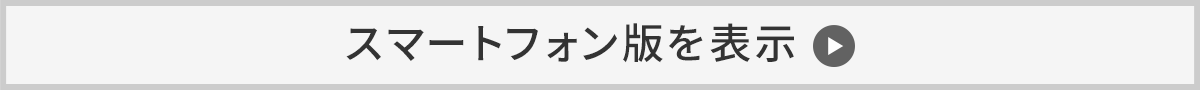
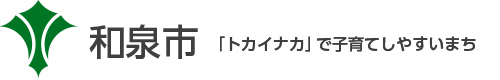


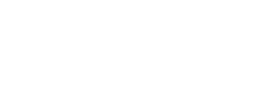
更新日:2024年11月01日