池上曽根遺跡の大型掘立柱建物~柱の年代再調査 同じ建物の中に700年も古い柱が含まれていたことが判明!~
7月10日提供
和泉市教育委員会、泉大津市教育委員会、国立歴史民俗博物館などからなるグループは、弥生時代を代表する遺跡「池上曽根遺跡」の大型掘立柱建物の柱材について、年輪幅および酸素同位体比を用いた2つの異なる年代測定を実施しました。
その結果、1997年に報告された1本は紀元前52年に伐採されたことが再確認されましたが、他の柱からは、紀元前52年から最大で700年も古い年代が得られ、1つの建物の柱に大きな年代の隔たりがあったことが判明しました。これほど大きな年代差のある木材で構築された建造物は、日本では類例がなく、非常に特殊な存在と言えます。
経緯と結果
池上曽根遺跡は、和泉市と泉大津市にひろがる、弥生時代の環濠集落遺跡です。1990年より始められた史跡整備に伴う発掘調査によって、集落の中心部から26本の柱からなる大型掘立柱建物の跡がみつかり、そのうち18本の柱材が良好な状態で残っていました。このうち辺材が残る「柱12」の年代が、当時の年輪年代測定法(年輪幅に基づく手法)により「紀元前52年」と判明しました。この年代は弥生時代の「定点」のひとつとされています。
その後、年輪幅による年輪年代測定法の暦年標準パターンが、データの追加によって高精度化しました。また、同位体分析技術の著しい発展によって、新しい年輪年代法である「酸素同位体比年輪年代法」が実用化に至りました。
今般、池上曽根遺跡において、この2つの年輪年代法を用いて、 30年ぶりに柱材の再調査を行いました。1990年代に調査された柱12を含む柱材5点と、酸素同位体比年輪年代については、未調査であった柱材1点をあわせて対象としました。
その結果、柱12の年代は紀元前52年が再現され、前回の測定を裏付けました。この柱には辺材および樹皮直下年輪が残っていて、この年代は樹木の伐採ないし枯死年を示しています。一方、他の柱材の年代は柱12よりも大幅に古く、紀元前782年や紀元前221年といった様ざまな年代を示しました。また、今回新たに酸素同位体比で測定した柱材の年代は紀元前92年で、柱12に近い年代となりました。
この測定結果は、年輪幅および酸素同位体比の年輪年代法で整合しました。これほど大きな年代差のある木材で構築された建造物は、日本では類例がなく、非常に特殊な存在といえます。
この記事に関するお問い合わせ先
〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 教育委員会生涯学習部 文化遺産活用課
電話: 0725-99-8163(直通)
ファックス:0725-41-0599
メールフォームでのお問い合わせ
- このページに関するアンケート
-
より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。

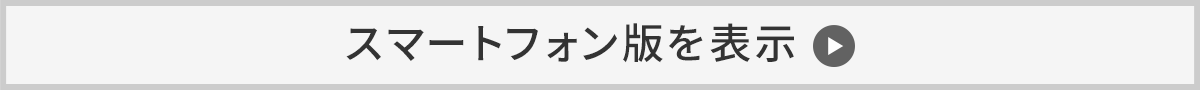
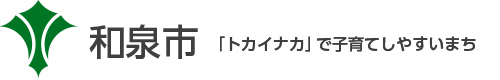


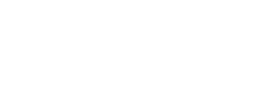
更新日:2024年07月10日