史跡池上曽根遺跡令和6年度発掘調査の現地説明会を開催!
9月19日提供
和泉市教育委員会では、令和8年度の池上曽根史跡公園一部リニューアルオープンに伴う史跡池上曽根遺跡範囲確認調査を国庫補助事業として令和6年6月より実施しています。調査面積は185平方メートルです。
今回の調査で、集落中心部で古墳時代の木棺墓群、弥生時代の大型掘立柱建物の一部、国内で類例が見られない焼土遺構などを検出しました。
これまで詳細の分からなかった集落中心部の様相の一部が分かったことから現地説明会を開催します。
【ポイント】
1.古墳時代中期の木棺墓群を確認。令和5年度調査と合わせて11基を確認した。
2.弥生時代の大型掘立柱建物の柱穴と考えられる土坑を多数確認した。
3.国内で類例の無い弥生時代の焼土遺構を確認した。用途や機能については不明であるが、大きな議論を生むであろうと考えられる。
【現地説明会】
日時:令和6年9月21日(土曜日)
説明:第1回 午前10時~ 第2回 午後1時30分~
第3回 午後2時30分~ (各回30分程度)
JR阪和線信太山駅下車 徒歩10分
南海本線松ノ浜駅下車 徒歩30分
(注意)会場に駐車場はありませんので、なるべく最寄の公共交通機関をご利用ください。車でお越しの方は、池上曽根史跡公園をご利用ください。
池上曽根遺跡の歩み
和泉市池上町から泉大津市曽根町にかけて広がる池上曽根遺跡は、国道26号建設に先立つ発掘調査で、大きな溝によって集落が囲まれた弥生時代の環濠集落であることがわかりました。近畿地方を代表する集落遺跡として、1976(昭和51)年、集落の中心部分約11万5千平方メートルが国史跡に指定されました。
1990(平成2)年から史跡整備事業に伴う発掘調査を始め、2001(平成13)年5月に指定地全体の約3分の1が史跡公園として開園しました。その間、1995(平成7)年には集落中心部で弥生時代最大級の大型掘立柱建物やくりぬき井戸が見つかり、また、大型掘立柱建物に遺されていた柱が紀元前52年に伐採されたことが判明するなど、弥生時代研究に大きな足跡を刻みました。2020(令和2)年度に史跡池上曽根遺跡保存活用計画を策定し、それに基づき2023(令和5)年度より整備工事を行っています。
令和6年度調査の位置と目的
令和5・6年度発掘調査を行っている場所は、集落の中心部にあたり、これまでの研究で「高い地形」と称され、集落内で重要な施設があると考えられてきました。しかし、これまで当地で発掘調査は行われたことがなく、今回が初の発掘調査となります。本発掘調査は集落中心部の様相を明らかにすることを大きな目的としています。
令和6年度調査の概要
令和5年度調査分と令和6年度調査分の調査区をあわせて、調査面積は385平方メートルです。令和6年度調査において確認された遺構は、古墳時代中期の木棺墓群(令和5年度調査で6基確認)、弥生時代中期後半の大型掘立柱建物の柱穴と考えられる土坑、列島内で類例の無い焼土遺構などです。
古墳時代中期の木棺墓は、令和5・6年度調査で11基確認しました。令和5年度調査の木棺墓群は溝で囲われていましたが、令和6年度確認分はその外側に位置しているため、グループが異なっていたと考えられます。木棺墓内には須恵器の坏や高坏、石製紡錘車が、副葬品としておさめられていました。須恵器の特徴から、短い期間で木棺墓群が形成されたことが分かりました。ただし、木棺墓群に葬られた人びとが何処で暮らしていたのかは不明です。
弥生時代中期後半の大型掘立柱建物の柱穴と考えられる土坑は、令和6年度調査区で確認されたもので、平面形は一辺80~90センチメートルの方形を呈しています。しかし、それらの土坑には非常に多くの重複関係があり、現状では柱筋や柱痕の規模等の詳細は不明です。土坑内から、細片ではありますが、弥生時代中期後半と考えられる土器が出土しています。
弥生時代の焼土遺構は、調査区の西端で東西12m×南北5mの範囲で確認しています。焼土遺構は、エリアごとに特徴があり、1センチメートル大の焼土ブロックが飛散する部分、焼土が集まり盛り上がっている部分、焼土が平らな面になっている部分からなります。これらが何を意味するのか現状では分かっていませんが、建物で使われていた壁土を廃棄したもの、鋳造と関連した遺構・焼土を伴った建物等が考えられます。また、全国的に類例が無いため、東アジアに類例を求めなければならない可能性もあります。
令和6年度発掘調査の結果、弥生時代の集落中心部が現在史跡公園内に復元している大型掘立柱建物と同規模の建物で構成されていた可能性が高くなりました。さらに、それらに近接して、特徴的な焼土を伴った構造物があったことが分かり、また、古墳時代中期の木棺墓群は、和泉地域ひいては近畿地域の墓制を考える上で、重要な発見となりました。
この記事に関するお問い合わせ先
〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 教育委員会生涯学習部 文化遺産活用課
電話: 0725-99-8163(直通)
ファックス:0725-41-0599
メールフォームでのお問い合わせ
- このページに関するアンケート
-
より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。

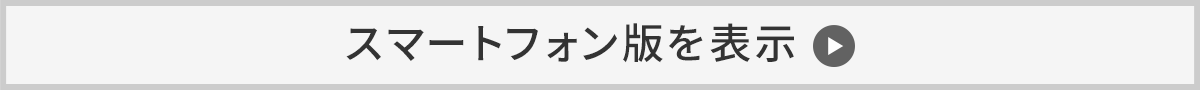
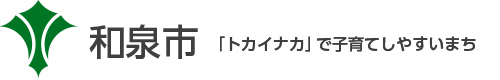


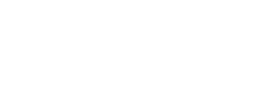
更新日:2024年09月19日