軽減・減免制度について
軽減制度
当該年度の前年の所得が基準以下の場合に、保険料の均等割額と平等割額が軽減されます。ただし、世帯全員の所得が判明していないと軽減が行われません。軽減割合は加入者の人数および世帯主と加入者の所得によって決定されます。
所得が基準以下の場合の軽減制度
- 7割軽減:世帯の前年中所得が基礎控除(43万円)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯
- 5割軽減:世帯の前年中所得が基礎控除(43万円)+(加入人数×30.5万円)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯
- 2割軽減:世帯の前年中所得が基礎控除(43万円)+(加入人数×56.0万円)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯
給与所得者等の数とは、世帯主(国民健康保険に加入していない方も含む)と加入者の内、
次のいずれかに該当する方の人数のこと。
1.前年の給与収入が55万円を超える方(専従者給与収入は除く)
2.前年の公的年金収入が60万円を超える方(65歳以上の場合は125万円を超える方)
(注)
- 年金収入につき公的年金等控除を受けた65歳以上の方については、公的年金等に係る所得金額から15万円を控除して判定を行います。
(例)68歳の方で前年の公的年金収入が200万円ある場合
公的年金所得に係る軽減判定所得は、200万円-110万円(公的年金等控除)-15万円=75万円として軽減判定を行います。 - 分離長期・短期譲渡所得の特別控除がある場合、控除する前の金額で軽減判定を行います。また専従者給与、専従者控除がある場合は、控除する前の金額で軽減判定を行います。
(例)世帯主が妻に専従者給与として80万円支給している場合- 世帯主の軽減判定所得は営業所得に80万円を足した金額で計算します。
- 妻の軽減判定所得は給与収入から80万円を引いた金額で計算します。
未就学児の均等割額の軽減措置について
未就学児の均等割保険料が5割軽減されます。
令和7年度の軽減対象者:平成31年4月2日以降に出生の被保険者(6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者)
「所得が基準以下の場合の軽減制度」の対象である未就学児の場合は、軽減後の均等割減額の半分を軽減します。
産前産後期間の国民健康保険料が減額されます
対象となる方
国民健康保険被保険者で出産(予定)日が令和5年11月1月以降の方
対象期間
出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間、以下「産前産後期間」といいます。)
(注)出産とは、妊娠85日以上の出産をいいます。死産、流産(人口妊娠中絶を含む。)早産された方も含みます。
対象保険料
出産される方の産前産後期間の所得割額及び均等割額
届出先
和泉市役所保険年金室又は和泉シティプラザ出張所の窓口
オンラインによる申請も受付しております。
申請方法
オンラインからの申請 → オンライン申請はこちら
窓口で申請する場合、下記届出書と必要書類を提出してください
【届出に必要な書類】
≪出産前に届出される場合≫
・本人確認書類(運転免許証等)
(注)別世帯の方が申請される場合は世帯主からの委任状が必要となります、
・届出書
・出産予定日、単胎妊娠又は多胎妊娠の別を確認することができる書類(母子健康手帳の写しなど)
(注)多胎妊娠の場合は人数分の母子健康手帳の写しが必要となります。
≪出産後に届出される場合≫
本人確認書類(運転免許証等)
(注)別世帯の方が申請される場合は世帯主からの委任状が必要となります。
・届出書
・出産日の分かるものは原則不要
(注)被保険者と子が別世帯の場合は、出生証明書などの出産日及び親子関係を明らかにする書類が必要です。
・減額対象となる場合、届出書の提出後、概ね2週間程度で保険料更正通知を送付します。
・申請内容に不備がある場合は連絡させていただくことがあります。
また、国民健康保険被保険者が出産をしたときに支給される出産育児一時金や、国民年金保険料の産前・産後期間の免除制度があります。
「倒産・解雇などによる離職(特定受給資格者)」や「雇い止めなどによる離職(特定理由離職者)」をされた人へ
65歳未満で下記の条件に該当する人は、国民健康保険料が軽減されます
- 雇用保険の特定受給資格者(例:倒産・解雇などによる離職)
- 雇用保険の特定理由離職者(例:雇い止めなどによる離職)
- 上記1、2で雇用保険受給資格者証又は雇用保険受給資格通知の離職理由が
11、12、
21、22、23、
31、32、33、34
のいずれかに該当する方。
軽減内容
保険料の所得割額の算定において、前年の給与所得を100分の30として算定を行います。給与以外の所得は対象になりません。
手続き方法
軽減を受けるには届出が必要です。雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知を和泉市役所保険年金室または和泉シティプラザ出張所にてご提示ください。また、オンラインでの申請も可能です。雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知がない場合は、この軽減制度の適用にはなりません。
オンライン申請はこちら
軽減期間
軽減期間は、離職の翌日から翌年度末までの期間です。国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き軽減の対象となりますが、会社・職場の健康保険などに加入するなど国民健康保険の資格を喪失すると終了します。
減免制度
災害による被害や所得の減少、事業の休廃止、失業などにより保険料のお支払いが困難になった場合に、一定の基準により、申請月以降の保険料が減免される場合があります。なお、保険料決定前には減免の受付ができませんので、保険料決定後(6月1日以降)にお手続きをお願いします。
所得減少による減免申請については、オンラインでの申請も可能です。
オンライン申請はこちら
・減免申請後、概ね2週間程度で結果を通知します。
・申請内容に不備がある場合や疑義が生じる部分があった場合は、連絡させていただきます。
・納付済保険料は減免対象外となります。
| 減免の区分 | 所得減少 | 災害 | 拘禁 | 旧被扶養者 |
| 対象保険料 | 所得割額を所得減少率に準じて減免 (減少率は国保加入者全員の前年所得の合計額と今後の見込み所得の合計額により算出) |
所得割額・均等割額・平等割額を 罹災の程度に応じて減免 |
所得割額・均等割額を100%減免 (単身加入の場合、平等割額も100%減免) |
所得割額を100%、均等割額を50%減免 (国保加入者が旧被扶養者のみの場合、平等割額も50%減免) |
| 対象期間 | 申請月から申請月の属する年度末まで | 申請月から申請月の属する年度末まで | 拘禁されている期間 | 所得割額…当分の間 均等割額・平等割額…2年間 |
| 対象事由 | 国保加入者の今後の見込み所得が令和6年と比較して30%以上減少している場合 | 震災、風水害、火災などにより居住する住宅が著しい被害を受けた場合 | 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁された場合 | 会社・職場の健康保険などに加入している人が後期高齢者医療制度に移行したときに、被扶養者が65歳以上で国民健康保険へ加入する場合 |
| 必要書類 |
・本人確認書類 ・現在の収入が分かる書類の例 |
・本人確認書類 (居住する住宅の証明に限る) |
・本人確認書類 ・在所証明書 |
・本人確認書類 |
| 備考 |
|
・減免に該当する罹災の程度は次のとおりです(罹災証明書の記載内容にて判定を行います。) 【全壊・全焼・大規模半壊】 【半壊・半焼】 【火災による水損又は床上浸水】 (注)上記以外の内容(一部損壊など)は減免の対象外です (注)被災した月から起算し、最大12か月までの範囲内で翌年度も延長申請(申請月以降の保険料が減免対象)が可能です。 |
・申請時現在でも拘禁されている場合、対象期間は年度末までになりますので、来年度時点でも拘禁されている場合には再申請が必要になります。 ・在所された方が住民票上単身世帯であった場合には、減免ではなく国民健康保険の資格喪失の手続きになります。 |
・国民健康保険組合に加入している人が後期高齢者医療制度に移行した場合は減免の対象外になります。 ・軽減制度の7割軽減・5割軽減の適用を受けている場合は、その年度は均等割額・平等割額の減免は行われません。また2割軽減の適用を受けている場合は、その年度の均等割額・平等割額の減免は30%のみとなります。 |
この記事に関するお問い合わせ先
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 市民生活部 保険年金室 国民健康保険担当 賦課徴収グループ
電話: 0725-99-8129(直通)
ファックス:0725-45-9352
メールフォームでのお問い合わせ

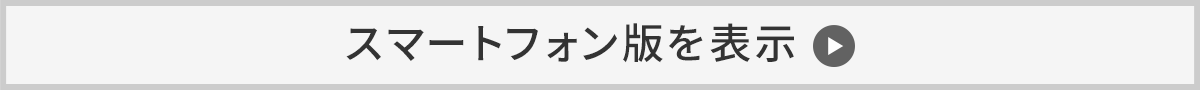
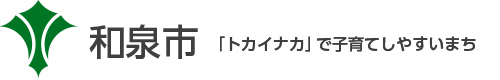


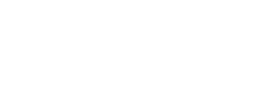
更新日:2025年05月12日